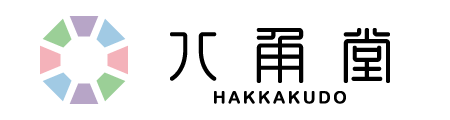脂質を選ぼう
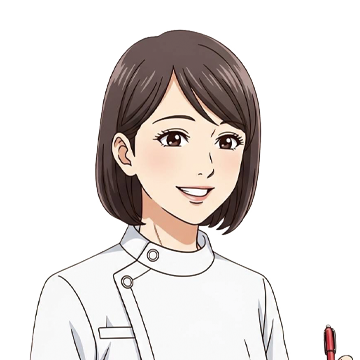
こんにちは。
長野県小諸市にある、ちょっと食事にめんどくさい美容鍼灸院「八角堂」の八角です。
私は、食べたくないものを食べるなら、食べない選択を選びます。
食に対して、少しめんどくさい人間です。
普段から糖質制限を行い、糖化を予防しています。
殆どカフェインは摂りません。
グルテン、大豆タンパク、カゼイン等は避け、塩や脂にも気をつけています。
なぜ脂が大切なのか
私たちの体は約37兆個の細胞から構成されています。
ひとつひとつの細胞にはそれぞれ「細胞膜」という膜で区切られていますが、この細胞膜の主成分が脂質(脂肪酸)なのです。
細胞膜は単なる仕切りではなく、栄養素の取り込み、老廃物の排出、情報伝達、酵素の活性化など、生命活動の根幹を担っています。
もし質の悪い脂を摂ったら?
質の悪い脂を摂取し続けると、以下のようなことが起こると考えられます。
・炎症が慢性化
アレルギー、関節炎、肌荒れ
・心血管疾患のリスク
動脈硬化、高血圧、心筋梗塞
・ホルモンバランスの乱れ
生理不順、更年期症状の悪化
・脳機能の低下
記憶力低下、うつ症状
・細胞の老化促進
早期老化、がんのリスク増加
例えばガソリンやプラスチックとほぼ同じ分子構造とされている油脂を摂ったら、その油脂は「私はいい油脂です」という顔をして細胞膜に張り付き、細胞の柔軟性を損ないます。
ひとつひとつの細胞の柔軟性が私たちを作っているのに、そんな最小単位から機能不全を起こされては、不定愁訴に悩まされるのは目に見えますね。
そうして引き起こされた不定愁訴は、慢性的な疲労感、頭痛、肌荒れ、喘息・花粉症・アトピー等のアレルギー症状、ホルモンバランスの乱れなど、様々な不調となって、私たちの身体に現れます。
特に現代人は、オメガ6系脂肪酸(サラダ油、コーン油など)の過剰摂取とオメガ3系脂肪酸(魚油、亜麻仁油など)の不足により、理想的な比率「1:1〜1:4」が、「1:10」や「1:50」という極端に偏った状態になっています。
これが体内の炎症を促進し、様々な体調不良の温床となっていると言われています。
摂るべき脂
積極的に摂るべき脂は、以下の通りです。
- オメガ3系
亜麻仁油、えごま油、小型青魚(イワシ、サバ、アジ) - 一価不飽和脂肪酸
エキストラバージンオリーブオイル、アボカド - 中鎖脂肪酸
ココナッツオイル(未精製) - ナッツ類
生くるみ、アーモンド(無塩・無添加)
普段の調理には動物性の飽和脂肪酸(牛脂、ラード)、ココナツオイルをお勧めします。
飽和脂肪酸は安定していて、常温で固まっている油で、酸化しにくく加熱に強いのが特徴です。
ココナツオイルには抗菌作用もあります。
生食用にはエキストラバージンオリーブオイル、亜麻仁油、エゴマ油を。
オリーブオイルの加熱は酸化が早くなり、身体にとって有害な物質へと変化するためお勧めしません。
避けるべき油は、トランス脂肪酸であるマーガリン、ショートニングど。
トランス脂肪酸とは、液体の植物油を個体にする「水素添加」という加工過程で生まれる人工的な脂肪です。つまり水素化合物ってことです…。
身体に必要な脂肪酸であるEPAやDHAの邪魔をし、アレルギー症状の悪化、心血管リスクの増加、脳機能の低下、精神的な不調を引き起こします。
WHOでは総摂取のエネルギーの1%未満が推奨され、アメリカでは2015年から全面禁止ですが、日本では規制されていません。
また酸化した脂も摂取は推奨しません。
加熱されたリノール酸を多く含む植物油、光や酸素に晒されて劣化した脂です。
酸化した脂は、「過酸化脂質」という有害物質に変化し、細胞の膜やDNA、酵素を破壊。
炎症を促進し、老化や病気の原因となります。
家庭でも脂の再利用はやめましょう(揚げ油を取っておく、ドレッシングを作って冷蔵庫で保管する、など…)
最後に、加工油脂や安価な植物油にも騙されないようにしましょう。
「植物油脂」「植物油」表示のものは、パーム油の可能性があります。パーム油はラードより飽和脂肪酸が多く、環境ホルモン様作用のものもあります。
加工過程にて、ヘキサン等の有害が化学溶剤が使用されることもあり、精製過程で栄養素が失われます。複数の油が混合されていることも。
日本の食品はかなり規制が緩く、海外では、日本用に国内では規制されているものを輸出している例もあります。
「日本人は勉強しないからいいや」と、思われているかもしれませんね。
まず知って、良い物を摂る前に、悪い物を摂らないようにしていきたいですね。
脂を買う際の5つのルール
良質な脂を選ぶ際は、以下の5つのルールが大切です。
①遮光瓶を選ぶ
光は酸素の1000倍も油の酸化を進めます。
特にオメガ3系脂肪酸は非常に酸化しやすいため、必ず遮光瓶(濃い色のガラス瓶)に入ったものを選びましょう。
透明なプラスチック容器はNGです。
②小容量(250ml程度)を選ぶ
開封した瞬間から酸化は進みます。
大容量を買って長期間使うより、小容量を短期間で使い切る方が、常に新鮮な油を摂取できます。
③「圧搾法(コールドプレス)」表示を確認する
「抽出法」で作られた油は、ヘキサンなどの有毒溶剤を使用し、高温での脱色・脱臭処理が行われています。
「圧搾法」「コールドプレス」「低温圧搾」と明記されたものを選びましょう。
④有機JAS認定を優先する
農薬や化学肥料を使わずに育てられた原料から抽出された油は、有害物質の残留リスクが低く、より安全です。
⑤製造年月日の新しいものを選ぶ
油は時間が経つほど酸化します。
製造年月日を確認し、できるだけ新しいものを購入しましょう。
良質な脂の「正しい摂取」で体調改善を実感
良質な油を選んだら、次は「正しい摂取法」が重要です。
まず、オメガ3系の油(亜麻仁油・えごま油)は 絶対に加熱してはいけません。
サラダにかける、納豆に混ぜる、スムージーに加えるなど、そのまま摂取してください。
目安は1日大さじ1杯程度です。
加熱調理には、牛脂やラードなどの飽和脂肪酸や、ココナッツオイルを使用しましょう。
ただし、高温での長時間加熱は避け、中温以下での調理を心がけてください。
加熱による脂の酸化や性質変化を防ぐためです。
また、オメガ3系の油を摂取する際はビタミンE と一緒に摂りましょう。
体内でも酸化は進むため、ナッツ類やアボカドなど、天然のビタミンEを含む食品と組み合わせることで、効果を最大化できます。
生のくるみなんてオメガ3とビタミンEを一緒に摂れますね。
また、保存は必ず冷蔵庫で行い、3〜6週間以内に使い切りましょう。
開封後は空気に触れる時間を最小限にするため(酸化を防ぐため)、使用後はすぐに蓋を閉めることも大切です。
良質な脂への切り替えは、私たちの身体を構成する、約37兆個とも言われる細胞のひとつひとつに影響します。
細胞から健康になり体内の炎症を抑えることで、慢性的な体調不良からの根本的な解放につながります。
まずは今使っている脂を見直すことから始めてみませんか?
長野県小諸市の鍼灸院「八角堂」では、若干マニアックな健康オタクの院長が、お身体のお話をお伺いします。
脂の他にもグルテン、カゼイン、糖質制限、お塩など、お身体や食事のお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。